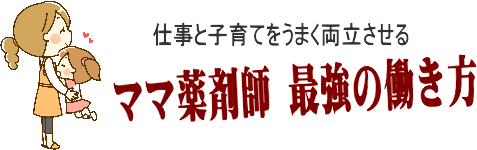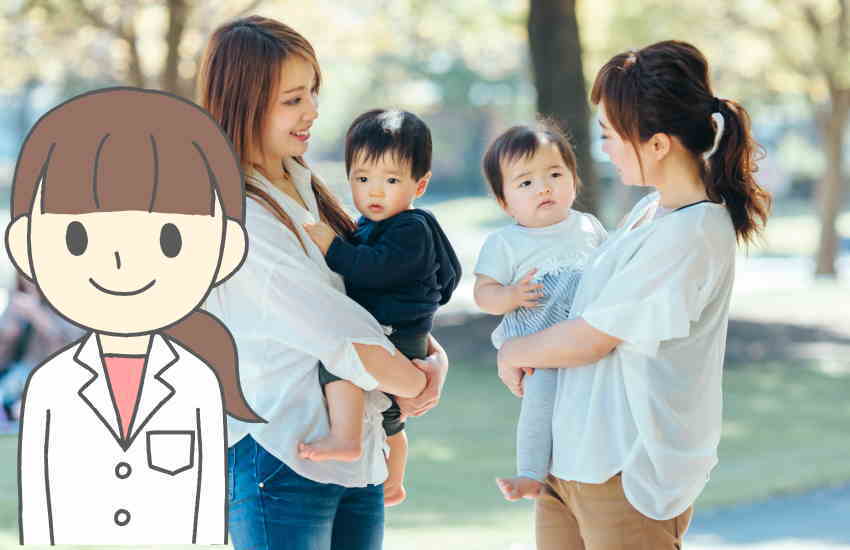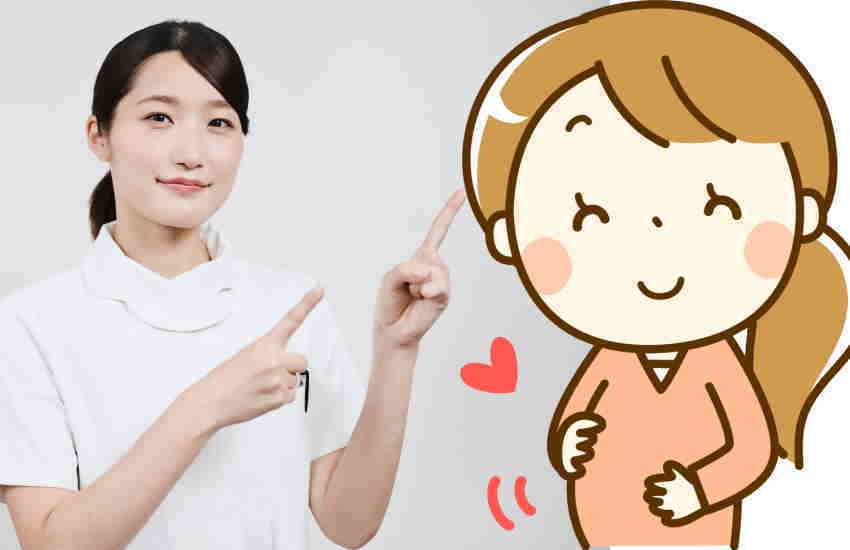20年のブランクがあっても、薬剤師として復職することは十分に可能です。
服薬指導や監査といった責任の重い業務を避け、ピッキングや予製などの裏方業務に特化した職場を選べば、医療事故のリスクを最小限に抑えながら安心して働けます。
現在、薬剤師業界は深刻な人手不足に直面しており、ブランクのある薬剤師でも歓迎される環境が整っています。
48歳での復職は決して遅くなく、むしろ子育て経験を通じて培った責任感や丁寧さが評価される年代です。
本記事では、長期ブランクがある元病院薬剤師の方が、無理なく安全に復職するための具体的な方法をご紹介します。
医療現場に戻ることへの不安は当然のことですが、適切な職場選びと準備をすれば、あなたの薬剤師免許は再び輝きます。
ブランク20年の薬剤師でも復職できる理由と現実

薬剤師免許には更新制度がなく、20年前に取得した資格も現在有効に使えます。
業界全体の人手不足により、ブランクのある薬剤師を積極的に受け入れる職場が増加中です。
服薬指導や監査を担当しない裏方業務なら、段階的に現場感覚を取り戻せます。
【薬剤師免許に期限はない】20年ブランクでも資格は有効
薬剤師免許には有効期限が設定されておらず、更新手続きも不要です。
20年前、30年前に取得した免許であっても、法的には現役の薬剤師と同じ資格として扱われます。
医師免許や看護師免許と同様に、一度取得すれば生涯有効な国家資格なのです。
ただし、免許が有効であることと実務能力は別の問題として考える必要があります。
医薬品の知識や医療制度は20年間で大きく変化しており、かつての知識だけでは対応できない場面も多いでしょう。
それでも免許という「入場券」を持っていることは、復職への第一歩として非常に重要な強みになります。
実際に、50代や60代でもブランクから復職し、活躍している薬剤師は全国に数多く存在します。
年齢やブランク期間よりも、「どの業務から始めるか」という職場選びこそが成功の鍵を握っているのです。
薬剤師不足の現状が長期ブランク者にとって追い風になっている
厚生労働省の調査によると、薬剤師の需要は年々増加しており、特に地方や郊外では深刻な人手不足が続いています。
調剤薬局の新規開設ラッシュや、病院での病棟薬剤師配置の義務化により、薬剤師の求人倍率は高止まりしている状況です。
この人手不足により、採用側の意識も大きく変化しました。
以前なら敬遠されがちだった「ブランク10年以上」の薬剤師も、今では貴重な戦力として歓迎されます。
特に調剤薬局チェーンや派遣会社では、ブランク薬剤師専用の復職支援プログラムを用意するケースが増えています。
求人広告を見ると、
「ブランク20年OK」
「裏方業務からスタート可」
といった文言が目立つようになりました。
採用側も、すぐに服薬指導をしてもらうのではなく、できる業務から徐々に担当してもらう柔軟な姿勢を持っています。
この追い風を活かさない手はありません。
「できる業務」から始める復職スタイルが主流になっている
現代の薬剤師復職支援では、
「できない業務」を無理に押し付けるのではなく、「できる業務」から段階的に始めるアプローチ
が主流です。
最初はピッキング(薬を棚から取り出す作業)や予製(軟膏の混合、一包化の準備)などの裏方業務に専念し、慣れてきたら徐々に業務範囲を広げていきます。
この段階的復職のメリットは、精神的な負担を最小限に抑えられる点にあります。
いきなり患者対応や監査を任されると、プレッシャーで続かなくなるケースが少なくありません。
しかしピッキングや予製なら、薬剤の知識を思い出しながら、自分のペースで作業できます。
実際の復職者の多くが、この方法で成功しています。
最初の3ヶ月は裏方業務のみ、
半年後から簡単な監査補助、
1年後に服薬指導デビュー
といった具合です。
焦らず、自分のペースで階段を上っていけばよいのです。
【48歳からの薬剤師復職は決して遅くない】同世代の成功事例
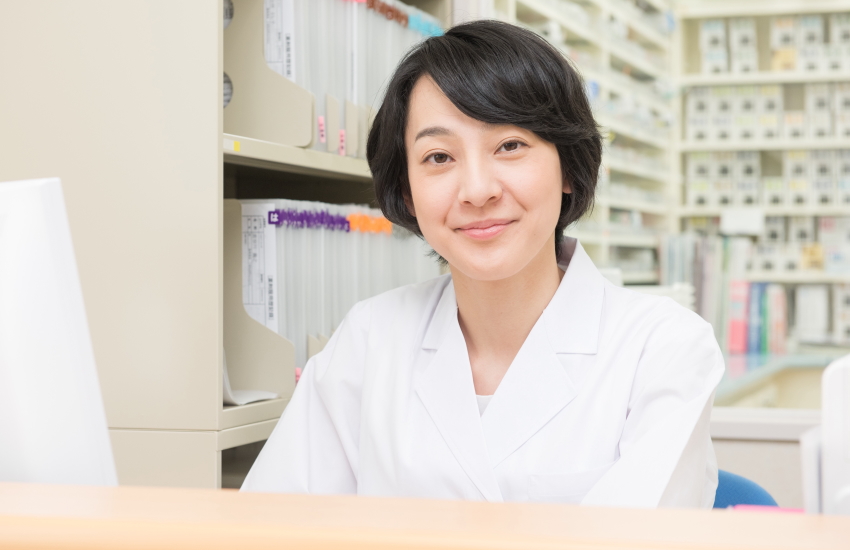
48歳という年齢は、薬剤師の復職において全く不利ではありません。
むしろ子育て経験を通じて培った忍耐力、コミュニケーション能力、責任感といった「人間力」が評価される年代です。
若手薬剤師にはない落ち着きや丁寧さは、職場で重宝されます。
彼女は最初の半年間は裏方業務のみに専念し、その後徐々に調剤補助へステップアップしました。
現在では後輩の指導も任されています。
患者対応が一切ない環境で働くことで、医療事故への不安から解放され、やりがいを持って勤務しています。
年齢やブランク期間は、適切な職場選びの前では障害になりません。
ブランク20年の薬剤師におすすめの服薬指導・監査なし「ピッキング・予製中心」の職場

調剤薬局の裏方業務、病院の調剤室内作業、医薬品卸のピッキングセンター、製薬会社の包装部門など、患者対応や監査責任のない職場は意外と多く存在します。
派遣会社を活用すれば、業務内容を事前に詳しく確認した上で働き始められます。
これらの職場では医療事故リスクが低く、ブランク薬剤師でも安心して働けます。
調剤薬局のピッキング専任スタッフ―薬剤師資格を活かせる裏方業務
大手調剤薬局チェーンを中心に、ピッキング専任の薬剤師を配置する店舗が増えています。
処方箋を受け取った後、薬剤師が棚から必要な医薬品を取り出す「ピッキング」作業に特化した役割です。
患者と直接対面することはなく、調剤室内での作業に集中できます。
ピッキング専任スタッフの具体的な業務内容は以下の通りです。
- 処方箋の内容に基づき、棚から医薬品を正確に取り出す
- 取り出した薬剤を調剤台に準備し、監査薬剤師に引き継ぐ
- 薬品の在庫管理や発注業務のサポート
- 返品薬剤の整理や期限チェック
- 薬局内の整理整頓や清掃
最終的な監査や服薬指導は別の薬剤師が担当するため、責任の重さが軽減されます。
ただし、ピッキングミスは調剤過誤につながる可能性があるため、丁寧さと正確性は求められます。
それでも、患者の前で説明する必要がないという点で、心理的ハードルは大幅に下がります。
時給は地域によって異なりますが、パートで1,800円〜2,200円程度が相場です。
週2〜3日、1日4〜5時間といった短時間勤務も可能で、家庭との両立がしやすい働き方といえます。
病院の調剤室内業務―注射薬調製や軟膏混合などの調製業務
病院薬剤部では、病棟への医薬品供給や注射薬の調製といった「裏方業務」が多く存在します。
外来患者への服薬指導や窓口対応を避け、調剤室内での調製業務に特化した働き方が可能です。
特に中規模以上の病院では、業務が細分化されており、希望に応じた配置が実現しやすくなっています。
病院調剤室での主な裏方業務には次のようなものがあります。
- 注射薬のミキシング(点滴への薬剤混合)―クリーンベンチ内での無菌調製
- 軟膏・クリームの混合調製―処方に応じた濃度調整
- 内服薬の一包化や粉砕―嚥下困難患者向けの調製
- 病棟への定数配置薬の補充と管理
- 医薬品の在庫管理とオーダリングシステムへの入力
注射薬調製は無菌操作の技術が必要です。
しかし、研修制度が整っている病院が多く、未経験からでも学べます。
軟膏混合は病院薬剤師時代の経験が活かせる業務で、ブランクがあっても比較的スムーズに対応できるでしょう。
病院勤務のメリットは、チーム医療の一員として働ける点です。
孤独感を感じにくく、困ったときに相談できる環境が整っています。
パート薬剤師の募集も多く、午前中のみ、週3日といった柔軟な働き方が可能です。
医薬品卸・物流センターのピッキング業務―患者対応ゼロの選択肢
医薬品卸会社や物流センターでは、薬剤師資格を持つピッキングスタッフを求めています。
病院や薬局からの注文に応じて、倉庫内から医薬品を集める業務が中心です。
患者と接する機会は一切なく、医療事故のリスクも極めて低い職場といえます。
物流センターでのピッキング業務の特徴は、医療現場とは異なる「物流」の視点で働ける点です。
医薬品を「治療に使うもの」ではなく「商品」として扱うため、精神的なプレッシャーが軽減されます。
温度管理や期限管理といった物流特有の知識も身につきます。
勤務時間は比較的規則的で、夜勤や休日出勤が少ないのも魅力です。
時給はピッキング専門の場合1,500円〜2,000円程度と、調剤薬局よりやや低めですが、残業がほとんどなく、体力的な負担も軽いといえます。
ただし、倉庫内での立ち仕事が中心となるため、ある程度の体力は必要です。
また、冷所保管が必要な医薬品を扱う冷蔵エリアでの作業もあります。
それでも「患者の命に直結する判断をしなくてよい」という安心感は、何物にも代えがたいメリットでしょう。
製薬会社の包装・品質管理業務―医療現場から離れた働き方
製薬会社の工場や品質管理部門では、薬剤師資格を持つスタッフを求めています。
医薬品の包装工程の管理、原材料の品質チェック、製造記録の確認といった業務が中心です。医療現場とは完全に離れた環境で、薬剤師免許を活かせる選択肢となります。
品質管理部門では、製造された医薬品が規格に適合しているかをチェックします。
成分分析や溶出試験といった試験業務に携わることもあり、理系の知識を活かせる環境です。
調剤業務とは全く異なるスキルセットが求められますが、丁寧な研修制度がある企業が多く、未経験からでも挑戦できます。
包装工程の管理では、医薬品の包装状態や表示内容が適切かを監視します。
GMP(医薬品製造管理及び品質管理基準)に基づいた記録管理も重要な業務です。
デスクワーク中心で、体力的な負担が少ない点も特徴といえます。
給与は正社員の場合、年収350万円〜450万円程度が相場です。
パート・派遣での募集は少なめですが、契約社員からスタートして正社員登用を目指すルートもあります。
医療現場のプレッシャーから完全に離れたい方には最適な選択肢です。
【ブランク20年からの薬剤師復職準備】最低限やるべき勉強と研修

復職前の準備として、都道府県薬剤師会や民間企業が提供する復職支援研修の受講が有効です。
eラーニングシステムを活用すれば、自宅で自分のペースで学習できます。
勉強内容は、薬価改定や後発医薬品への切り替えなど、基本的な変更点を押さえる程度で十分スタート可能です。
研修を受けずに就職し、OJTで学ぶ選択肢もあります。
【都道府県薬剤師会の復職支援研修】無料または低価格で受講可能
全国の都道府県薬剤師会では、ブランクのある薬剤師向けの復職支援研修を定期的に開催しています。
受講料は無料または数千円程度と低価格で、薬剤師会に未加入でも参加できるケースが多くあります。
研修内容は基礎的な調剤知識の復習から、最新の医療制度まで幅広くカバーされています。
東京都薬剤師会を例に取ると、年に数回「復職支援研修会」が開催されており、半日〜1日のプログラムとなっています。
午前中に講義形式で医薬品知識や制度変更を学び、午後は実習形式で調剤機器の使い方を体験できます。
参加者の多くがブランク10年以上の薬剤師で、同じ境遇の仲間と出会える貴重な機会です。
研修を受けることで得られるメリットは、知識の更新だけではありません。
「自分だけが取り残されているわけではない」という安心感や、講師である現役薬剤師からの励ましが、復職への自信につながります。
履歴書に「○○県薬剤師会復職支援研修修了」と記載できることも、採用側に対するアピールポイントになります。
各都道府県薬剤師会のウェブサイトで開催情報を確認できます。
申込みは先着順のことが多いため、興味があれば早めに問い合わせることをお勧めします。
ブランク薬剤師向けeラーニング―自宅で学べる復職準備
対面研修に参加する時間が取れない方には、eラーニングシステムが便利です。
日本薬剤師研修センターが提供する「JPALS(ジェイパルス)」や民間企業の復職支援プログラムでは、オンラインで学習できるコンテンツが充実しています。
自宅のパソコンやスマートフォンで、自分のペースで進められます。
JPALSは薬剤師の生涯学習支援システムで、基礎から応用まで幅広い講座が用意されています。
ブランク薬剤師向けには「調剤基礎講座」「服薬指導の基本」「医薬品情報の読み方」といった復習コンテンツがあります。受講料は年会費制で、月額換算すると2,000円程度と経済的です。
民間の調剤薬局チェーンでも、独自のeラーニングシステムを持つ企業があります。
例えば、大手チェーンの中には、入社前に無料でeラーニングを受講できる制度を設けているところもあります。
採用が決まってから入社までの期間に、自宅で準備学習ができるのです。
eラーニングのメリットは、何度でも繰り返し視聴できる点です。
理解できなかった部分を巻き戻して確認したり、メモを取りながらゆっくり学習したりできます。
通勤時間や家事の合間といった隙間時間を活用すれば、無理なく知識を更新できます。
【最低限押さえるべき勉強内容】薬価改定と後発品への変更を中心に
復職前の勉強で最も重要なのは、「医薬品の名前の変化」を理解することです。
20年前に使っていた先発医薬品の多くが特許切れとなり、ジェネリック医薬品(後発医薬品)に置き換わっています。
同じ成分でも複数のメーカーが製造しているため、商品名を覚え直す必要があります。
具体的には、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 一般名処方の普及―成分名で処方される仕組みの理解
- 後発医薬品への変更ルール―変更可能な条件と手順
- 薬価改定の仕組み―2年に1度の薬価見直しの影響
- ハイリスク薬の管理―特に注意が必要な医薬品の種類
- 電子お薬手帳の普及―患者の服薬情報管理の変化
難しい理論や最新のエビデンスを完璧に理解する必要はありません。
むしろ「現場で何が変わったか?」という実務的な変化点を把握することが重要です。
医薬品の添付文書や薬価を調べる際は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)のウェブサイトや薬価サーチなどの無料データベースが便利です。
スマートフォンアプリも充実しており、「添付文書」「薬価」といったキーワードで検索すると、複数の無料アプリが見つかります。
【研修なしでも働ける職場もある】現場でのOJTを重視する企業
実は、復職前に特別な研修を受けなくても採用してくれる職場は多く存在します。
特にピッキングや予製といった裏方業務中心の職場では、「現場で覚えてもらえれば大丈夫」というスタンスの企業が少なくありません。
入社後のOJT(On-the-Job Training、実地訓練)で丁寧に指導する体制を整えています。
大手調剤薬局チェーンの中には、ブランク薬剤師専用の入社研修プログラムを持つ企業もあります。
入社後1週間〜1ヶ月は座学と実習を組み合わせた研修を受け、その後配属店舗でマンツーマンのOJTを受けます。研修期間中も給与が支払われるため、収入面での不安もありません。
派遣会社を通じた就業の場合、派遣会社が独自の研修制度を用意していることがあります。
派遣先に行く前に、派遣会社の研修施設で調剤機器の使い方や基本的な業務の流れを学べます。派遣先でつまずかないための「予行演習」ができるのです。
「研修を受けてから復職したい」という気持ちは自然ですが、研修を待っている間に時間だけが過ぎてしまうのももったいないことです。
研修制度が充実した職場を選べば、働きながら学べます。
完璧な準備よりも、まず一歩を踏み出す勇気が大切です。
ブランク20年の薬剤師の復職先の探し方と面接で伝えるべきポイント

薬剤師専門の転職サイトを活用し、
「ブランク歓迎」
「ピッキング業務中心」
といった条件で絞り込んで検索します。
派遣会社を利用すれば、業務内容を詳細に確認してから働き始められます。
面接では、ブランク理由や希望業務を正直に伝えることが、適切なマッチングにつながります。
パートや派遣からスタートし、段階的に正社員を目指すキャリアパスも現実的な選択肢です。
【薬剤師専門転職サイトの活用法】「ブランク歓迎」「裏方業務」で絞り込む

薬剤師の求人探しには、薬剤師専門の転職サイトが最も効率的です。
一般の求人サイトと異なり、薬剤師特有の条件(ブランク年数、業務内容、勤務形態など)で細かく絞り込めます。
代表的なサイトには「薬キャリ」「ファルマスタッフ」などがあります。
検索時に設定すべき条件は以下の通りです。
- ブランク
「10年以上可」「ブランク歓迎」にチェック - 業務内容
「ピッキング」「調剤補助」「裏方業務」などのキーワード - 雇用形態
「パート」「派遣」(まずは短時間から始める場合) - 勤務地
自宅から通える範囲に絞る - 勤務時間
「1日4時間〜」「週2日〜」など柔軟な条件
多くの転職サイトでは、登録すると専任のキャリアアドバイザーが付きます。
アドバイザーに
「20年のブランクがある」
「服薬指導や監査は避けたい」
と正直に伝えれば、条件に合った求人を紹介してくれます。
求人票に載っていない「非公開求人」を紹介してもらえることもあり、選択肢が広がります。
まずは複数のサイトに登録することをお勧めします。
サイトごとに扱っている求人が異なるため、3〜4社に登録すれば、より多くの選択肢から選べるからです。
登録や利用は完全無料で、しつこい営業電話を避けたい場合は「メール連絡希望」と伝えれば配慮してもらえます。
ブランク20年の薬剤師におすすめの転職エージェント

「ブランクが20年もあるけど…」
そんな不安があるあなたが、いきなり一般募集で薬剤師の仕事を探すのはかなりハードルが高いですよね。
そんなときにこそ、転職エージェントが力になってくれます。
私のおすすめは「ファルマスタフ」と「薬キャリ」です。
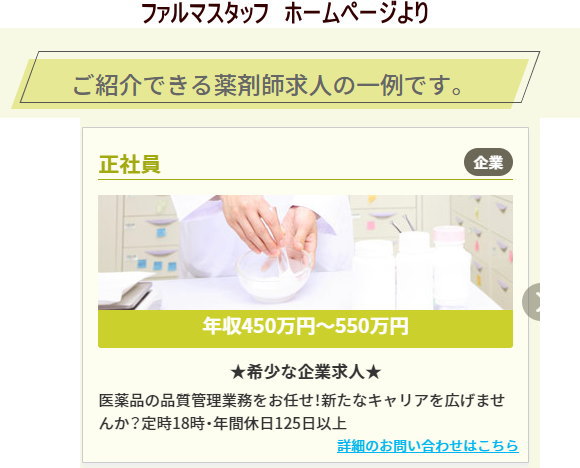
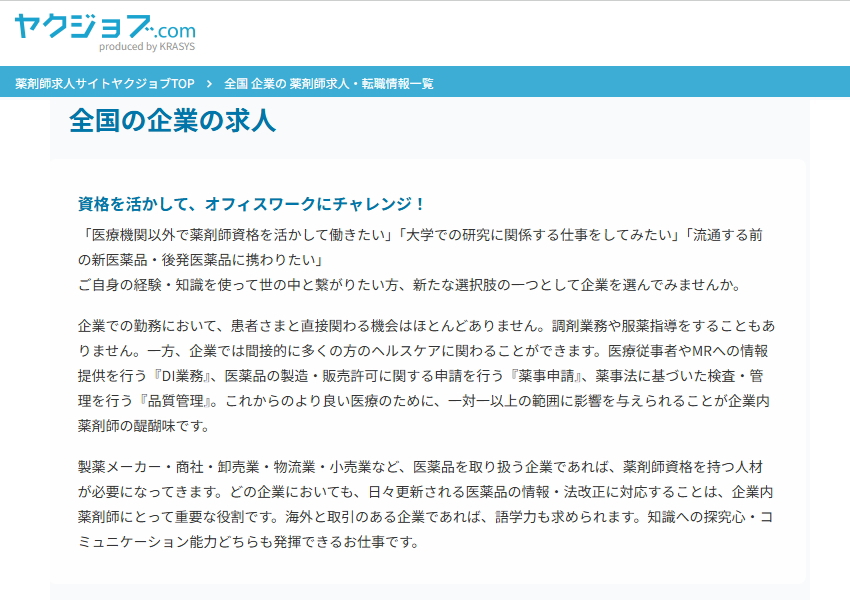
「毎日が同じことの繰り返し…」 「この先、自分の薬剤師人生はどうなるのだろうか?」 調剤薬局で5年、10年と勤務した方に多い漠然とした不安ですよね。 患者さんの安全を守る重要な仕事だと分かっていても、心のどこかで漠然とし …
派遣会社を使うメリット―業務内容を事前に細かく確認できる
派遣会社を通じた就業は、ブランク薬剤師にとって非常に有利な働き方です。
最大のメリットは、派遣先の業務内容を事前に詳しく確認できる点にあります。
派遣会社の担当者が派遣先に直接訪問し、
「どの業務を担当するのか?」
「服薬指導はあるのか?」
「監査は求められるのか?」
といった細かい点を確認してくれます。
直接雇用の場合、面接時に詳しく聞きにくい雰囲気があったり、入社後に「話が違う」と感じたりすることがあります。
しかし派遣なら、派遣会社が間に入ってくれるため、希望を伝えやすく、ミスマッチを防げます。
実際に働き始めてから問題があれば、派遣会社に相談して調整してもらうことも可能です。
時給も派遣のほうが高めに設定されていることが多く、パート直接雇用より200円〜500円高いケースもあります。
社会保険や有給休暇も派遣会社から提供されるため、福利厚生面でも安心です。複数の派遣先を経験することで、自分に合った職場のタイプが見えてくるというメリットもあります。
薬剤師専門の派遣会社には「ファルマスタッフ」「薬キャリ」「MC-ファーマネット」などがあります。
派遣会社によって得意とする職場タイプが異なるため、2〜3社に登録して比較するとよいでしょう。
登録時の面談で、ブランクの不安や希望する業務内容を詳しく伝えることが重要です。
【面接で正直に伝えるべきこと】「医療事故が怖い」は隠さない
面接では、ブランク期間や復職への不安を隠さず正直に伝えることが、長期的な成功につながります。
「医療事故が怖い」
「服薬指導は避けたい」
といった率直な気持ちを伝えることで、採用側も適切な配置を考えてくれます。
無理に背伸びして採用されても、入社後に苦しむことになりかねません。
面接で伝えるべきポイントは以下の通りです。
- ブランク理由
「子育てのため」と素直に説明(詳細な家族構成まで話す必要はない) - ブランク期間
「約20年」と正確に伝える - 復職の動機
「子育てが一段落し、資格を活かして社会復帰したい」 - 不安な点
「いきなり服薬指導は難しいため、ピッキングなど裏方業務から始めたい」 - 自分の長所
「丁寧さ」「責任感」「学ぶ意欲」など子育て経験で培ったもの
「医療事故が怖い」という表現が直接的すぎると感じる場合は、
「患者様の安全を第一に考えると、まずは裏方業務で現場感覚を取り戻してから、段階的に業務範囲を広げたい」
といった言い回しもあります。
前向きな姿勢を示しつつ、慎重なアプローチを希望していることを伝えましょう。
逆に、面接で聞いておくべきことも重要です。
「ピッキング専任として採用されるのか、将来的に服薬指導も求められるのか」
「研修制度はどうなっているのか」
「先輩薬剤師のサポート体制はあるのか」
といった点を確認しておくと、入社後のギャップを防げます。
このあたりも転職エージェントが悉皆rとサポートしてくれますから、安心してください。
【パート・派遣から正社員へ】段階的に業務範囲を広げるキャリアパス
いきなり正社員としてフルタイム勤務を目指すのではなく、パートや派遣からスタートする段階的なキャリアパスが現実的です。
最初は週2〜3日、1日4〜5時間の短時間勤務で裏方業務に専念し、慣れてきたら勤務日数や時間を増やしていきます。
その後、正社員登用の機会があれば検討すればよいのです。
実際の段階的復職モデルを示すと、以下のような流れになります。
- 最初の3〜6ヶ月はパート勤務でピッキング・予製のみを担当
現場の雰囲気や業務の流れに慣れます。
その後、簡単な調剤補助や在庫管理といった業務を追加し、1年後には一包化や軟膏調製など、より専門的な調剤業務にも携われるようになります。 - 自信がついてきたら、監査補助や簡単な服薬指導にも挑戦
ただし、無理に業務範囲を広げる必要はありません。
ピッキング・予製専任のまま、パート薬剤師として長く働き続ける選択肢も十分に価値があります。
あなたのペースで、あなたが安心できる範囲で働けばよいのです。
大手調剤薬局チェーンの中には、パートから正社員への登用制度を明確に設けている企もたくさんあります。
「パート勤務1年以上」
「週4日以上勤務」
といった条件を満たせば、正社員試験を受けられる仕組みです。
最初から正社員を目指すプレッシャーを感じることなく、まずはパートでスタートし、将来の選択肢として正社員を考えるとよいでしょう。
まとめ
20年のブランクがあっても、薬剤師として復職する道は確実に開かれています。
服薬指導や監査といった責任の重い業務を避け、ピッキングや予製といった裏方業務に特化した職場を選べば、医療事故への不安を最小限に抑えながら働けます。
薬剤師不足の現状は、ブランク薬剤師にとって追い風です。
調剤薬局のピッキング専任スタッフ、病院の調剤室内業務、医薬品卸のピッキングセンター、製薬会社の品質管理部門など、選択肢は多岐にわたります。復職前の準備として、都道府県薬剤師会の研修やeラーニングを活用すれば、自信を持ってスタートできるでしょう。
職場探しには、薬剤師専門の転職サイトや派遣会社の活用が効果的です。
面接では、ブランクや不安を正直に伝えることで、適切なマッチングが実現します。
まずはパートや派遣からスタートし、段階的に業務範囲を広げていくキャリアパスを描けば、無理なく復職を果たせます。
48歳でブランク20年でも薬剤師のp復職は決して遅くありません。
子育て経験を通じて培った責任感や丁寧さは、必ず職場で評価されます。
完璧な準備を待つよりも、できることから始める勇気こそが、復職への第一歩です。
あなたの薬剤師免許は、まだまだ輝き続けることができます。
ママ薬剤師にとって、 産後の復帰 育休明けの復帰 で悩むことって少なくありません。 なぜなら、以前と同じようにバリバリ働けないからです。 どうしても幼い子供をかかえたままでは子供のことが気になって仕事も手につきません。 …